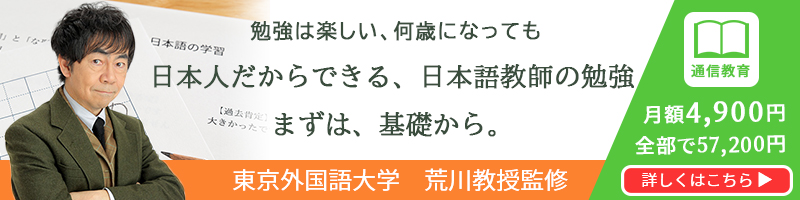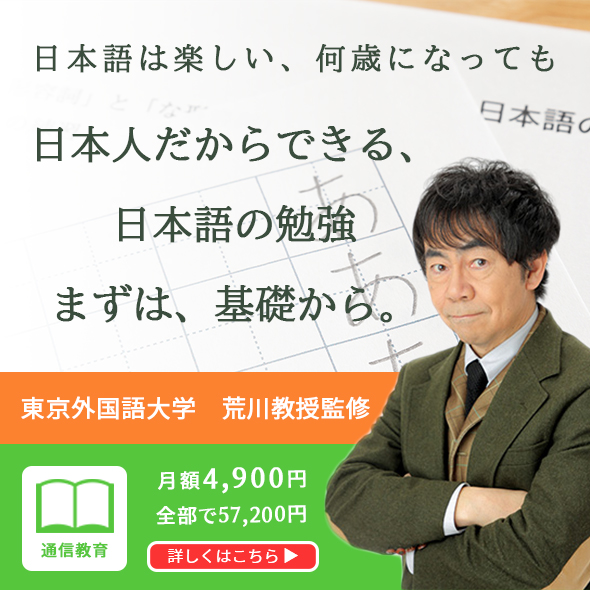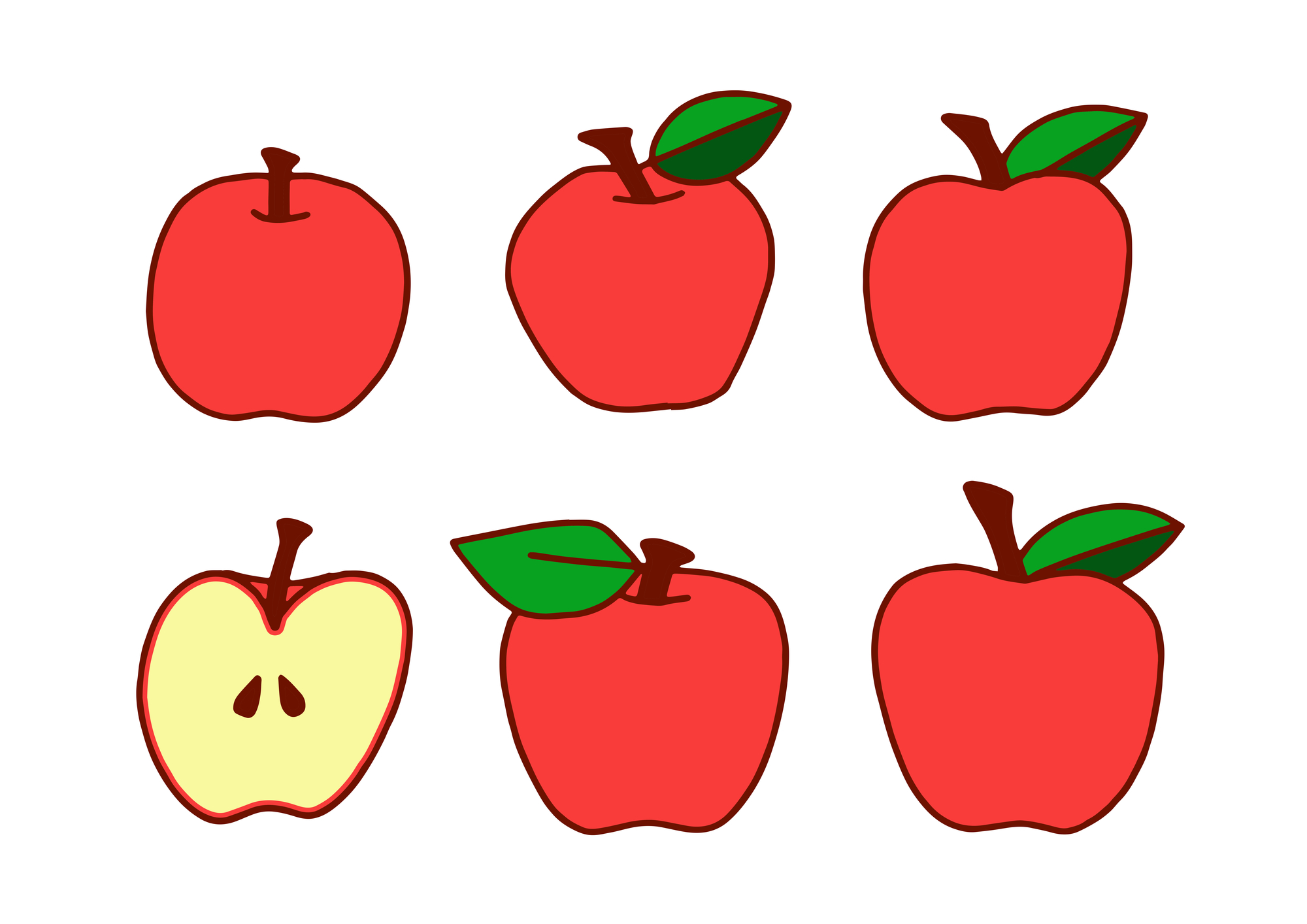最近よく「共生社会」とか「多文化共生」などということばをききますよね。
皆さんは、このことばをどのように捉えていらっしゃいますか。
文:志賀玲子 講師
夫の赴任地からの帰国をきっかけに専業主婦から日本語教師に。
都内日本語学校にて数年間勤務後、大学院へ進学。大学院修了後、日本語教師養成講座講師、大学講師に。
現在、大学にて留学生教育の他、日本の学生への初年次教育及び日本語教授法等の科目を担当。
「共生」について
ちょっと寄り道して、まず、「共生」という言葉から考えてみましょう。
私は、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞の4つのデータベースを利用して過去の新聞記事を検索してみました。
「共生」という言葉が新聞で使われ始めたのは、1980年代のようです。その当時の使われ方は様々なのですが、どのような使われ方をしているか、いくつか紹介しますね。
例えば、朝日新聞では、「人間は本来、緑と共生と共生すべき宿命」をもつ、「農業・地場産業と都市生活者との共生」、昆虫と植物の共生、「木や鳥や虫と共生する自然人」などのような使われ方をしています。
日経新聞では、機械と人間との共生、共生する樹木、(カイガラムシとアリ)の共生、技術と芸術の共生、企業と社会との共生、共生的社会的企業、という組み合わせで出てきます。
毎日新聞には、「若者と老人が共生できる」、シカとコガネムシ類の共生、世界諸国民との共生(社会党「新宣言」)、大自然との共生、(社会主義と資本主義の)共生の時代(ゴルバチョフ・ソ連書記長)、東京湾との共生、というように登場します。
最後に読売新聞では、東洋と西洋の共生、自然との共生、ダニとカビの共生、アジアをはじめ世界の諸国民と共生、などです。
2つのベクトル
上の共生についてのフレーズを見ていると、「従来の姿を守ろう」というベクトルと「新しいものを生み出そう」というベクトルの、2つの視点で分けることができそうですよね。
「従来の姿を守ろう」というベクトルは、自然との共生や生物同士の共生など、もともとある自然の営みの(再)発見や(再)認識について、あるいは壊されつつあるそれぞれの関係を守るべきだとの主張が込められていたように思えます。例としては人間と自然の共生や、昆虫と植物の共生、共生する樹木などがあげられます。
これに対して、「新しいものを生み出そう」というベクトルは、新しい創造物の誕生や社会の変化の中で、意識的に取り組むべきこと、あるいは努力して対応すべき姿勢について訴えているような感じがしませんか。例としては機械と人間との共生や技術と芸術の共生、企業と社会との共生などです。「新しいものを生み出そう」というベクトルに含まれるもののうち、東洋と西洋の共生、世界の人々との共生などは、多文化共生につながる流れであると言えますね。皆さん、いかがでしょうか。
「共生社会」について
次に、「共生社会」ということばになると、1987年以降に出現します。当時は、なんと「男女共生社会」というフレーズで出てくる場合が圧倒的に多いんです。
1985年5月に男女雇用機会均等法が成立している影響でしょうか。1980年代後半は「共生社会」というと「男女共生社会」が連想されていたようなのです。
一方で、多民族共生社会や定住外国人との共生社会など、いわゆる「多文化共生(社会)」につながることばが少しずつ出現する様子も見られるようになってきます。
「共生社会」と言ってもその時代によって使われるフレーズや文脈が異なるのですね。なんとなく使ってしまっていることが多いのですが、ちょっと注意をすると時代を反映していて奥深さがありそうです。
さてさて、新聞に「多文化共生」というフレーズが最初に登場したのは1993年1月12日の毎日新聞です。その記事のタイトルは、「『地域』をキーワードに市民レベルの海外協力のあり方を考える開発教育国際フォーラム」というものです。「“地域”は“世界”を変えていく」というテーマで行われたフォーラムについての記事です。記事には「人権、環境、多文化共生、地域協力などをめぐる10の分科会での討論や体験学習を行う」とあるのですが、この場合の「多文化共生」が具体的に何を指しているかは記事だけからは判断できません。「多文化共生」という文言がなんとなく、既に自明のこととして共有されているようでもあります。
朝日新聞での初出は、1995年10月14日「多文化共生センター」(※1)へ衣替えした、との記事です。日経新聞は1995年7月31日、おおひん地区まちづくり協議会の「多文化共生の街づくり」について、読売新聞は1993年8月31日「多文化共生社会の実現に向けて、力強い作品を書き続けている」という文脈で出てきています。地域社会での取り組みの様子が伝えられているようです。
共生社会実現へ
このように、「共生」という言葉はもともとあらゆる場面で使われていたことがわかります。そして時代を反映しているようです。
ところで、「共生」や「多文化共生」という言葉は、その言葉自体がもつ美しく良きものという抽象的な価値観を含んでいますね。ですから、やがて、行政をはじめ、様々な場所でのキャッチフレーズとして使われるようになってきたようです。この考え方を皆が共通してもつことは、共生社会実現への第一段階としてとても必要なことだと考えられます。ただし、ここでちょっと注意が必要だと指摘する人たちがいます。
この言葉を掲げることによって、すでに自分たちが「良いことをしている」という気になってしまうということもその懸念材料のひとつです。実は本当に共生を実現させるためには、参加者すべての努力が必要なのです。そこには、時として不快な、そしてその不快さを乗り越えるべき強い意識が必要です。心地の良い言葉の裏にある苦の実態が隠されてしまうことがあることを、私たちは注意しなければならないようです。
同化を強いてしまうような危険性
例えば、私たちは、特に意図せず、同化を強いてしまうような態度をとる可能性があります。ここで、子どもに対する日本語教育を考える際の重要な視点をご紹介します。
ご自身もブラジル人であるリリアン・テルミ・ハタノ氏は、「本来学習者をエンパワーするための日本語」が「同化の道具」として教えられていることへの危機感を訴えています。ハタノ氏は、多様な背景をもつ子どもたちが日本社会で生きるに際しての日本語習得の必要性は認めつつ、「日本人らしく振る舞う」ことが押し付けられたり、「ネイティブ」のような日本語を求められる結果「不完全な日本語」話者だとの扱いを受け続けたりすることによる子どもの成長への弊害を主張しています。そして、こうしたことは社会的な問題として議論されるべき事柄である一方で、日本語教育に携わる、或いは携わろうとしている個人個人にも、「それぞれの学習者が必要としている日本語力を身につけさせるための教育がはたして提供されているのか」ということや「日本語教師として何を目指すのか」といったことについてじっくり考えるべきだと提言しているのです(※2)。
真の多文化共生社会の実現のためには、一人ひとりが社会的な視野をもち、かつ、自分が何をすべきか或いはできるかを考えることが重要だということを示唆しているものだとも言えます。自分がどう関わるか、どう関われるかについて熟慮し行動することは、多文化共生社会実現のために、私たち一人ひとりがもつべき姿勢なのではないでしょうか。
これまでの日本社会は、移動する人々を日本社会になじませるといった一方的で表面的で同化的なやり方で多文化共生社会を目指してきた感があります。でも、このやり方に危険性があることは明らかです。日本語教師という仕事は、多文化共生社会の実現に実際に関われる仕事です。しかし、一歩間違えれば、それは同化を強いることと等しくなってしまう危険性をも含んでいます。こういったことについては、是非立ち止まって考えてみるべきではないでしょうか。
多文化共生社会の図式
さてここで、非常にわかりやすい多文化共生社会の図式を紹介したいと思います。
共生について研究している志水宏吉氏は、相互に対話し関係を作り上げた結果新しい価値が創造される社会を、「A+B →A’+B’+α」という図式で端的に示し、これを求める共生社会としています(※3)。Aは社会のマジョリティ、Bはマイノリティを表しています。上記図式が表す意味は、マジョリティとマイノリティが出会ったとき、両者が変わり(A’、B’)、その過程で新たな価値や制度(α)などが生まれるということです。
かつて多くの社会で考えられていた同化主義は「A+B→A」と表されており、それに対する反省から生まれた考え方は、「A+B=A+B」で表されています。これは「多文化主義」または「文化多元主義」と呼ばれるものです。この場合、両者ともに変容は求められません。このうち、経済的にも文化的にもBが主体性をもちつづけAとの関係も良好であるなら「統合主義」となります。一方、BがBのままで存在できるもののAとの接点はなく孤立した状態にある場合「分離主義」となります。私は、文化多元主義から一歩進んだ「共生」、つまり、「A+B →A’+B’+α」を目指すモデルとした志水氏に賛同し、自分自身ができることとして日本語教育の現場での活動を進めています。
皆さんも、ご自身で「多文化共生」について考え定義してみてください。流行のようになんとなく使われている現在にあって、たちどまって、その意味を深く考えることはとても大切なことだと思います。そして、多文化共生社会のためにご自分ができることに一歩を踏み出してみませんか。
なお、志賀による本連載は今回が最終回となります。これまでおつき合いくださいましてどうもありがとうございました。
参考
※1)定非営利活動法人 多文化共生センター大阪」1995年1月17日の阪神・淡路大震災の発生が契機となり、同年10月に設立された。(日本財団のホームページより)
https://fields.canpan.info/organization/detail/1853340162
※2)リリアン・テルミ・ハタノ(2006)「在日ブラジル人を取り巻く『多文化共生』の諸問題」植田晃次・山下仁編著『共生の内実―批判的社会言語学からの問いかけ』三元社
※3)志水宏吉(2020)「私たちが考える共生学」志水宏吉・河森正人・栗本英世・檜垣立哉・モハーチ ゲルゲイ(編)『共生学宣言』大阪大学出版会